「競馬で大きく当たったけど、これって税金がかかるの?」「税務署に申告しないとまずい?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、競馬で得た払戻金には税金がかかるケースがあり、申告を怠ると後から税務署から督促状が届くこともあります。
中には、裁判にまで発展したケースも存在します。
この記事では、「いくらから税金がかかるのか」「税金を払わないとどうなるのか」「競馬の税金はバレるのか」などをわかりやすくまとめています。
記事のポイント
- 競馬の払戻金はいくらから税金がかかる?【基礎知識と計算例】
- 税金を払わないとどうなる?競馬の無申告で督促状が届く現実
- 競馬の税金は本当にばれる?ばれない?
- 裁判にまで発展した事例も!
- 競馬の税金に時効はある?5年と7年の違いを正確に理解しよう
- 競馬で負けても税金がかかる?損しても課税対象になる理由
競馬の払戻金はいくらから税金がかかる?【基礎知識と計算例】

競馬の払戻金にかかる税金は、所得税法に基づき「一時所得」または「雑所得」として扱われます。
普通に個人が馬券を購入している場合は「一時所得」となり、年間の利益が50万円を超えた場合に課税されます。
具体的には、以下の計算式で課税対象となる金額を算出します。
| 計算式 | (払戻金 − 購入金額) − 特別控除(最高50万円) |
| 課税対象 | 利益が50万円を超えた分 |
例えば、ある年に100万円の払戻金を得て、その年に馬券を60万円分購入していた場合、その利益は40万円となります。
この40万円は特別控除の範囲内なので課税対象にはなりません。
しかし、払戻金が130万円、購入金額が60万円であれば利益は70万円となり、50万円を超えた20万円が課税対象となります。
同じ「競馬でも職業的に大量の馬券を購入し、継続的に利益を出している」と見なされる場合は「雑所得」扱いとなり、より厳しい課税の対象になります。
税金を払わないとどうなる?競馬の無申告で督促状が届く現実

競馬で得た利益を申告せずに放置していると、税務署から「督促状」や「調査通知」が届く可能性があります。
特に、JRAや地方競馬のネット投票システム(即PAT、楽天競馬、SPAT4など)を利用している場合は、購入記録や口座情報がすべて記録に残るため、税務署が照会することが可能です。
たとえば、競馬で高額の払戻を得たあと、その金額を銀行口座に入金したとします。金融機関では一定額以上の入出金に対して、税務署に情報を提出する義務があるため、ここから発覚するケースもあります。
また、過去には税務署からの調査を受け、数百万円単位の追徴課税を課された事例もあります。申告を怠っていると、後になって本税に加えて加算税(最大40%)や延滞税が課されることもあるため、申告義務があるかも?と思った時点で、必ず対応するのが賢明です。
競馬の税金は本当にばれる?ばれない?
「申告しなければバレない」というのは誤解です。
実際には、税務署が各種データを活用して調査を行う仕組みが整っています。
その主な要因として、以下のようなものがあります。
ネット購入履歴が確認できる
即PATや楽天競馬など、オンライン投票にはアカウント情報・購入履歴・払戻金額がすべて記録されており、必要に応じて税務署が照会可能です。
銀行口座の入出金も監視対象
高額な振込や現金化が頻繁に行われている場合、銀行側から税務署に報告されることがあります。
マイナンバー制度との紐付けも進んでおり、特に高額取引はチェックの対象となりやすいです。
他の所得と不整合が出る
無職や年金受給者であるにもかかわらず、数百万円の入金があった場合、所得との整合性が取れず調査が入りやすくなります。
つまり、バレない前提で動くのは非常に危険です。
税務署は過去数年分にさかのぼって調査できる権限を持っており、数年後に突然通知が来ることもあります。
裁判にまで発展した事例も!

競馬で得た利益を申告せずにいた結果、実際に裁判沙汰になった事例もあります。
中でも有名なのは、2017年のいわゆる「競馬3億円申告漏れ事件」です。
この事案では、競馬で3年間にわたって総額3億円以上の払戻を受けながら一切申告していなかったことが発覚し、税務署から巨額の追徴課税を受けました。
この裁判のポイントは以下の通りです。
| 内容 | 判決のポイント |
|---|---|
| 馬券購入を反復継続していた | 「雑所得」として課税対象と判断された |
| 払戻金を申告していなかった | 追徴課税(本税+加算税+延滞税)が課された |
| 弁護士を通して争った | 最終的に国税の主張がほぼ全面的に認められた |
裁判にまで発展すると、金銭的負担はもちろん、世間への影響や精神的なダメージも大きくなるため、早めの対応が重要です。
競馬の税金に時効はある?5年と7年の違いを正確に理解しよう
税金の支払い義務には「時効」がありますが、状況によってその期間は5年と7年で異なります。
| 状況 | 時効期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 通常の無申告 | 5年 | 意図的でない場合 |
| 悪質な隠蔽や虚偽申告 | 7年 | 故意・偽装・隠蔽が認定された場合 |
なお、時効は「税務署が気づいたとき」ではなく、「本来申告すべき年の翌年3月15日からカウント」されます。
ただし、税務調査が始まるとその時点で時効は中断されるため、「逃げ切る」という考え方は極めて危険です。
競馬で負けても税金がかかる?損しても課税対象になる理由
意外な落とし穴として、「トータルで競馬に負けていても税金が発生する」ケースがあります。
これは、税務署が一時所得を馬券ごとに判断しているからです。
たとえば、年間で100万円分の馬券を購入し、払戻金が90万円であったとします。この場合、全体では10万円の損失です。
しかし、もしその中に「1万円の馬券で10万円当たった」ような大きな的中があった場合、その的中分だけで利益が9万円とみなされ、課税対象になる可能性があります。
つまり、「全体で損してるから大丈夫」とは限らず、個別の馬券の的中結果が課税対象となることがあるという点には注意が必要です。
総括
記事のポイントをまとめています。
- 競馬の払戻金はいくらから税金がかかる?【基礎知識と計算例】
- 税金を払わないとどうなる?競馬の無申告で督促状が届く現実
- 競馬の税金は本当にばれる?ばれない?
- 裁判にまで発展した事例も!
- 競馬の税金に時効はある?5年と7年の違いを正確に理解しよう
- 競馬で負けても税金がかかる?損しても課税対象になる理由
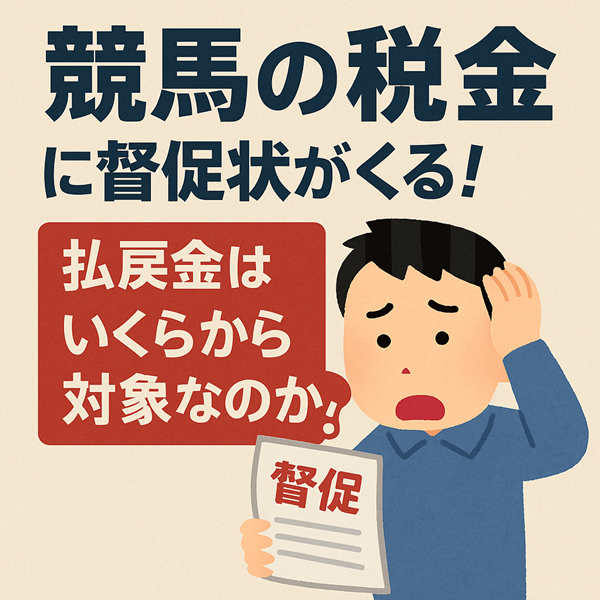


コメント